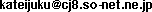「共感力」の講演会 [私が読んだ本]
9月初旬のことですが、「不登校親の会」が主催する講演会に行って来ました。
講演者は前回の記事でも紹介した元小学教諭で、現在は大学講師をされている【大和久勝】さんです。
「共感が育てる子どもの自立」をテーマに、大和久先生と子どもたちとのエピソードを交えながら、講演のタイトルにもなっていた「共感力」について話してくださいました。
先生は「共感力」という本も著されているので、その本の内容も交えながら、ここで紹介させていただきたいと思います。
本の巻頭には、伊吹文部科学大臣が、「いじめ」について、子どもたちに呼びかけている文章が載っていました。
「……(略)いじめられて苦しんでいる君は、けっして一人ぼっちじゃないんだよ。お父さん、お母さん、おじちゃん、おばあちゃん、きょうだい、学校の先生、学校や近所の友達、だれにでもいいからはずかしがらずに、一人で苦しまず、いじめられていることを話すゆうきをもとう。話せば楽になるからね。きっとみんなが助けてくれる」
現外務大臣の町村さんが文部大臣だった時(1998年)の、「文部大臣緊急アピール」についても触れています。
「子どもたちへ ナイフを学校に持ち込むな 命の重さを知ってほしい。……(略)君たちにもう一度言おう。悩みや不安は、遠慮なく友達やお父さん、お母さん、先生など大人たちに相談しよう。私たちは、君たちの言葉を受け止めたい」
大和久先生は、2人の大臣の言葉は、中身のない空々しいもので、子どもたちの生きるつらさや悩みに共感しているようには感じられないと書いています。上からの目線で、子どもたちを見下ろして語っているようで、大人の側や教育行政の責任者としての反省が感じられないと言うのです。
子どもの問題は、実は大人の問題と思っている私は、大和久先生の言葉に大いに共感しました。
「共感」について、書かれた部分で、特に印象に残っている箇所を前の記事とだぶりますが書いておきたいと思います。
困った子は困っている子 [私が読んだ本]
日々、子どもと関わっている学校の先生の本を読んで、これほど温かく満ち足りた感情が湧き上がってきたことはありません。こんなにすばらしい先生たちが、実際にいたのかと思うとうれしくなって、「日本の教育も捨てたものではないな」と明るい気持ちになりました。
いじめで子どもが自殺しても、不登校で苦しんでいる子どもがいても、マスコミ報道を見るかぎりでは、学校関係者は責任のなすりあいをするだけで、「つらかったね」「何も力になれないでごめんね」と、当事者である子どもを思いやる姿を見せていませんでした。そのことに私は、強い憤りを感じていたからです。
この本には4人の先生が登場しますが、こんな先生が学校に1人でもいてくれたら、いじめも不登校もなくなるし、子どもだけでなく、子育てに悩むお母さんたちも救われるに違いないと思いました。温かくて、人としての器が大きくて、指導力のある先生たちです。
先生たちが子どもに向かう姿勢は、本のタイトルにあるように「困った子」を「困っている子」として捉えるという見方です。
落ち着いて授業を受けられない子、問題行動を起こす子、不登校の子、学力不振の子等は、先生にとっては「困った子」と考えられてきました。
それに反して、「困る子」「困った子」を、その子自身が「困っている子」として見るという「子ども観」の転換を行います。
「困った子」を「困っている子」と捉えることで、子どもに対する接し方が大きく変わっていきました。子どもに向かうまなざしはあたたかくなり、子どもの生きづらさや苦しみに深い共感を持つようになって、しぜんに子どもに寄り添えることができるようになりました。(もっとも、この先生たちは発想の転換などしなくても、もともとそういう感性を持っていたような気がしますが)
副題には、『「軽度発達障害」(LD、ADHD、高機能自閉症、アスペルガー症候群)の子どもと学級、学校づくり』とありましたが、先生たちは通常の学級で、彼らにレッテルを貼ることなく、学級という集団の中で彼らの居場所と出番を作ることに心を砕きます。
「軽度発達障害」をどう見るか、という部分には以下のことが書いてありました。
(「軽度発達障害」というと、「軽いもの」と見られがちですが、決してそうではありません。子どもたちは、わかってもらえない、理解してもらえない苦しさ、つらさをかかえて過ごしています。「できない」ことを「できるはず」と見られ、「なぜあなたはできないのか」と否定的評価を繰り返し受け、自尊感情や自己肯定感を低めてしまっているのです。「自分なんて」「どうせだめなんだ」「いなけりゃいい」と口癖のように言います。………
まわりの子どもや大人たち、教師からも親からでさえも、理解されずにいる場合があります。そんな子ども達は自分が自分を理解できずに苦しみます。そんな中では、キレたり、パニックを起こしたりするしかないのです。)
先生たちとの関わりの中で、子どもたちが「だめだと思っていた自分」から「友だちからも認められる自分」に変身していく過程は、どのエピソードをとっても感動的で、胸がいっぱいになりました。
ADHD,高機能自閉症が疑われる小学1年のユウタと、先生の人間性が感じられる一場面を書き出してみます。
(「先生、また明日会おうね、さようなら」ユウタはそういって、手を振って歩きだした。が、すぐに立ち止まり、振り返って「先生、また明日会おうね、さようなら」と言って手を振った。また少し歩いては立ち止まり、振り返った。ユウタは何度も何度も同じことを繰り返しながら帰っていった。
私は彼と出会って初めて胸が熱くなった。ユウタの認められたい思いを痛いほど感じた。私はユウタを心底からかわいいと思った。この子といっしょにやっていこう、そう思った。)
この本を読んで、競争や管理で子どもたちを縛りつけるより、「困った子は困っている子」という子供観の転換が、教育関係者や親たち、大人たち、さらには子どもたちにまで広く浸透することが求められていると思いました。また、そうなってほしいと願わずにはいられませんでした。
実は、私は、この本の編著者で元小学校教諭の『大和久 勝』さんの講演会にも、つい最近のことですが行ってきました。不登校の子どもをもつお母さんたちにも、聞いていただきたかった内容なので、次回にでも紹介したいと思っています。
教室の悪魔 [私が読んだ本]
東京都児童相談センター心理司の山脇由貴子さんの著書「教室の悪魔」を読みました。この本が、今、学校で起こっている“子どもたちのいじめの実態”について書いた本であることは知っていたのですが、読むのがこわくて今まで避けていたのです。
想像通り、いじめのあまりの残酷さ、陰湿さに、読んでいて気分が悪くなってしまいましたが、子ども達が置かれている大変な状況を知ることができて、その分だけ子どもに寄り添うことができるかもしれないとも思いました。
前々から思ってはいましたが、「いじめられる側に原因があるのでは」などという言葉は、子どものいじめの実態を知らない能天気な大人のいう言葉で、「強くなりなさい」と同様、決して言ってはならない言葉だと痛感させられました。
クラス全員が悪魔と化して、たったひとりの子どもを、ありとあらゆる方法を使っていじめ抜いていくのです。いじめられ側には何の問題もないのに、いじめられる理由が、いじめが進行するなかで次々に作られていってしまうのです。
そして、いじめられる側には、「みんな嘘だと知ってやっている」ということがわかっているので、反論のしようがありません。
「一度いじめが始まると、そこに存在する全員が参加することが強要される。参加しないのは裏切り者である。子ども達は、いじめという悪に全員を参加させることで、大人に発覚するのを防ぐ。そして同時に、全員を参加させることで自らの罪悪感を薄め、悪を正義に変える」とも書いてありました。
正義感を持つことなど決して許されずに、今は傍観者でいることも許されず、自分の身を守るために、感情を鈍化させ、残酷になるしか方法がないのだと言います。
もし私自身が、全員が悪魔になってしまった教室で、毎日のように無視され、馬鹿にされ、汚い言葉でののしられ、嘲笑され、暴力を振るわれ、そのうえ自分の家族まで辱められたとしたら、どうすることもできないと思います。
たった一人で、クラス全員に立ち向かうことなど不可能でしょうし、いじめを解決してくれる大人がいるとも思えないからです。
また、加害者になどなりたくないのに、自分を守るために誰かをいじめてしまったら、そんな自分がいやでたまらなくなって、学校に行けなくなるかもしれません。
世界中の誰も信じられなくなり、心に深い傷を負ったまま、怖くて外にも出られなくなるかもしれません。心の病気にだってなってしまうことだって考えられます。
暗い内容ばかり書いてしまいましたが、私はこの本は、すべての大人に読んでほしいと思いました。親として、大人として、私たちがどうあるべきか、何をしなければならないかが見えてくると思うからです。
“いじめの実態”が書いてある部分は、目を背けたくなるのですが、『見えない「いじめ」を解決するために』という副題もついているように、希望のもてる本です。
第1章は、「いじめ」は解決できるで、本の著者の山脇さんと被害者の子ども、子どもの両親が心を一つにして、冷静に、賢明なやり方で学校関係者と辛抱強く話し合い、いじめを解決していきます。子どものつらさや悲しみ、親の子どもを思う気持ち、学校と向かい合う親の姿、山脇さんの人柄や姿勢に、深い感動を覚え胸がいっぱいになりました。
第2章は、大人に見えない残酷な「いじめ」で、いじめの具体例がいくつも挙げられていました。
第3章は、なぜクラス全員が加害者になるのか?で、いじめのメカニズムが解き明かされています。
第4章は、「いじめ」を解決するための実践ルールで、親にできること、すべきこと、絶対にしてはならないことが書いてあり、役立つ内容でした。
第5章は、「いじめ」に気づくチェックリストで、子どもの日常を丁寧に見るうえからも必要な内容だと思いました。
最後に、このブログを読んでくれているあなたがいじめられている側だとしたら、この著者のように、信用できる大人もいるんだということわかってほしいと思います。
そして、前にも書きましたが、いじめられている自分を否定することはしないでください。
加害者は悪魔ですが、あなたは悪魔に魂を売り払ってはいない、クラスで たった一人の子どもなのですから、それだけでもすごいことだと思います。
また、本書にも書いてありましたが、子どもが被害者であったとしても、保護者の方は、子どもの許可なく学校には行かないということも、守ってほしいと思いました。
大切なのは、いじめっ子の悪魔たちをやっつけることでも、学校の責任を問うことでもなくて、どうしたら子どもが安心して学校に通えるようになるのか、いじめを解決するために親や教師や、そして当の子どもたちはどうしたらよいかを考えることだからです。
この本を読んで、私が明るい気持ちになれたのは、いじめの解決策についてきちんと書いたあったからです。いじめが起きた場合に、親が学校に行かないほうがいいことまではわかっていたのですが、その先の解決法についてはわかっていませんでした。それがわかったことが、私にとっては大きな前進でした。
いじめを解決することは容易なことではありませんが、真剣に解決に取り組む親や教師やその他の大人たちがいて、そこに子どもたちを巻き込んでいけば、いいのだということがわかりました。
いじめ問題を、子どもの問題として捉えるのではなく、一人ひとりの大人の生きかたが問われているのだと考えることが、求められていると思いました。
重松清の「エイジ」 [私が読んだ本]
7年ほど前に中学生の甥に借りて読んだ「エイジ」を、今回は自分で買った文庫本でもう一度読み直してみました。
1回目のときも、時間を忘れて一気に読んでしまいましたが、2回目の今回も飽きることなく夢中で読みふけっていました。
それにしても著者の重松さんという人はすごい人です。大人なのに、どうしてこれほど中学生の気持ちがわかるのかと思います。エイジや、その周りの少年、少女たちを見事に描ききっていて、物語の世界の登場人物というより、まさに目の前にいる中学生たちという感じがするのです。
東京郊外のニュータウンに住むエイジは、地元の「桜ヶ丘東中学」に通う中学2年生で、14歳になったばかりです。父親は高校の教師、母親は専業主婦、高校生の姉もいて、エイジは、時々家族のことを“うざい”と思いながら、それでも家族のことが好きだと思うふつうの中学生です(エイジ自身は、何を基準にふつうと言われるのかわからないし、「ふつの中学生」という言葉にも馴染めないものを感じています)。
エイジの住む桜ヶ丘ニュータウンで「連続通り魔事件」が起きることから物語は始まります。犯人はエイジと同じクラスのタカやんでした。14歳の少年が起こした事件ということでマスコミは騒ぎ立て、先生たちは事件について何も説明しないまま、朝夕、校門の前で生徒たちに「声かけ運動」を始めます。
マスコミはタカやんのことを、「14歳の通り魔」とか、「少年A」とか、「犯行の動機はストレスとか、漫画の影響、ゆがんだ性欲」とか報じます。それに対して、エイジは違和感を覚えます。
エイジにとって、タカやんは親しい級友ではないにしても、姿や形が見えない不特定の14歳の通り魔の少年ではなくて、生身のタカやんだっからです。
「中学生」ということで、ひとくくりにされることにも抵抗感を持ちます。
また、エイジは考えます。犯人のタカやんはキレたかったから、あんなことをしちゃったんだろうか、自分もタカやんになる可能性がないとは言いきれないのではないのかと。
さらに、エイジは思います。「キレる」と言う言葉は、オトナが考えているのと違うんじゃないかと。我慢とか辛抱とか感情を抑えるとか、そういうものがプツンとキレるんじゃない、自分と相手とのつながりがわずらわしくなって断ち切ってしまうことが、「キレルる」なんじゃないかと。
そしてついに、エイジもキレたくなって、学校からキレ、家からキレ、桜ヶ丘という地元からもキレて、渋谷に出て行きます。道行く人たちのことを「こいつら、うざい」「死ぬほど、うざい」と思いながら、幻のナイフで次々に刺していきます。
エイジの親友のツカちゃんも、片思いの相手の相沢志穂も魅力的です。ツカちゃんはテレビのインタビューで「通り魔だからっつて、べつにいいんじゃないすか?」とサービス精神のつもりで答えて、大人たちのひんしゅくを買います。
けれど、事件から数ヵ月後にタカやんがクラスに戻ってきた時に、タカやんに本心をぶつけます。
「タカ、人間、後ろからいきなりやられたらよお、びっくりするんだよ。痛えんだよ。殴られる理由がなかったら、もっと痛えんだよ。わかってんのか。このバカ野郎、わかれよ。それ、わかんねえんだったら、てめえ、殺すぞマジ、死ぬまでぶっ殺してやるからな、そこんとこ、よろしくっ」
私は、ツカちゃんにこれだけ言われて、タカやんはかえってすっきりしたのではないかと思いました。
タカやんがどうして通り魔をやったのかについては、物語の最後まで触れられていませんでしたが、私はそれはタカやん自身にもよくわからなかったのではないかと思います。
中学生のこの時期は、自分自身を含めていろいろなことをまじめに真剣に考えて悩む時期だと思うのですが、考えがまとまらずに頭の中がもやもやしていて、自分でも自分のことがよくわからないのではないかという気がします。
大人だって自分のことはよくわからないのですが、だんだんと鈍感になっていって、考えないようにしている部分もあるのです。
ところで、エイジはどうなったでしょうか。自分のキレる気持ちに決着をつけることが出来たのでしょうか?好きな相手にうまく気持ちを伝えることができたのでしょうか。
共感できるところがたくさんある本だと思います。読み終わったら元気が出る本だと思います。悩んでいたことが吹っ切れるかもしれません。
まだ読んでなければ、ぜひ読んでみてください。
14歳 千原ジュニア [私が読んだ本]
狭い屋根裏部屋にカギをかけ、1年以上ひきこもっていた少年の物語は、
「これは、ある14歳の物語。パジャマを着た少年の物語。僕自身の物語。」から始まった。
大人によく怒られていた少年は、社会という枠の中に自分を囲い込もうとする大人から自分を守るために、勉強して、青い服を着る私立中学に合格した。
すると、少年が嫌っていた近所のおばさんは、急に態度を変え、少年によくしゃべりかけるようになった。けれど、少年がパジャマを着て表に出るようになると、見て見ぬ振りをした。同じ僕なのに、おばさんは青い服にしゃべりかけていたんだろう、と少年は思う。
みんなと同じ道を歩むことができなくて、同じやり方も進み方もできなくて、自分だけの道しか歩くことができない少年。それでいて、自分がどこに向かえばいいのかわからない、何をどうすればいいのか、何をどうしたらいいのかもわからない。
少年が、確実にわかっているのは、自分の行く道は自分にしか見つけられないということだけだった。
少年は、両親に対しても、心の中で叫び続けている。
「お母さん、僕が僕のために走るべきレース場を見つけるまでもう少し待ってください。お父さん、僕が僕のために進むべき道を見つけ出すまでもう少し我慢してください。
僕は今、それを一生懸命に探しているところなんです。」―――――――と。
私はこの本を読んでいて、胸に突き刺さるものを感じた。
少年が自分の進むべき道をみつけるために、自分自身との孤独な闘いを続け、もがき苦しんでいる様子が、痛いほど伝わってきたからだ。
本当の自分に出会うために、思春期から自立への一歩を踏み出すために、これほど真剣に悩み苦しんで、自分と向き合い、自分と対話した少年がいたことを、私は知らない。
世の中の大部分の大人は、こういう少年に対して、「甘ったれるな」、「つべこべ言わずにやることをやればいいんだ」、「みんなが行く学校にどうして行かない」と非難したり、あるいは、少年の母親のように「頭がおかしくなったのではないか」と思うかもしれない。
逆の言い方をすれば、青い服を手に入れた少年は、他の青い服を着た少年たちと同じように、何の疑問ももたずに、新たにスタートした青いレースに参加して、ゴールを目指すことが出来たら、どんなに楽だったかと思う。
けれど、感受性の豊かな少年は、それが自分の道ではないと気づいてしまったのだ。鈍感ではいられない、不器用にしか生きられない少年は、与えられた一本の道を進むことができなかったのだ。
人生は一本道ではなく、いくつもの道があることを、少年は知っていたのだろう。
少年の気持ちがわかるというより、私はこういう感性をもつ少年が好きだ。世の中で生きていくためには、鈍感さも必要だと思うし、鈍感でなければ生きづらい世の中であることは認めるけど、鈍感ではないことが、若さの特権ではないかとも思う。
私は感性が豊かで、不器用な少年や少女たちに心が引かれる。
多分、私の中にも、同質の部分があるからだろう。
一方、この本の中の母親の気持ちも、母親の立場としてはよくわかる。
壁にいくつもの穴をあけるわが子に対して、気が狂ってしまったのではないかと思い、夕食のみそ汁にこっそりと精神安定剤を入れたり、変な名前の学校や奇妙な名前の病院のパンフレットを取り寄せたりする。
また、少年と顔を合わせることを避けようとしてパートに出たりもするが、耐えに耐えた挙句に「なぜそんなふうになってしまったの」「私たちのどこがいけなかったの」「この家にいるのが嫌なら出て行けばいい」「もう限界」と、少年に向かって鋭い言葉をぶつけたりもする。
私は、少年も、少年の両親もちっとも悪くないと思う。
それでも、不登校やひきこもりが、自分の家庭の中で起きてしまったら、親も子どももどうしたらいいのかわからないのが実情だろう。
少年のように、自分の道を見つけられればいいと思う。
そして私は、少年のパジャマを脱がせることになった少年のお兄ちゃん役になれれば、と思う。